喪中の新年挨拶はどうする?自分が喪中・相手が喪中の完全マナーガイド
大切な人を亡くした年のお正月は、いつもとは違う静かな気持ちで迎えるものですよね。
そんなとき、ふと疑問に思うのが「喪中の新年挨拶って、どうすればいいのだろう…?」ということ。
喪中につき新年のご挨拶を、「あけましておめでとう」と言わない方がいいって本当?
このガイドでは、
- 自分が喪中の場合
- 相手が喪中の場合
の2つに分けて、一番丁寧で無理のない喪中新年挨拶の仕方をわかりやすくまとめました。
後半では、挨拶文のテンプレートをキレイなPDFとして保存・編集できるPDFelement(スマホでも使えるPDF編集アプリ) の上手な活用方法もご紹介します。

1. 喪中とは?新年挨拶で気をつけたい基本
まず知っておきたいのが、「喪中」には厳密な法律や決まったルールがあるわけではない、ということです。
一般的には、身近な家族を亡くし心静かに過ごす期間として、
- 両親・義両親
- 配偶者
- 子ども
- 兄弟姉妹
- 祖父母
などが「喪中の対象」と言われます。
喪中のあいだは、つぎのような「お祝いごと」を控えるのが昔からの慣習です。
- 「おめでとう」を含む賀詞
- 年賀状や年始の挨拶
- 正月飾りを華やかに飾ること
- お祝いの席への参加
もちろん地域や宗派、ご家庭によって考え方は少しずつ違いますが、「新年をお祝いする言葉は控える」という点は、ほとんど共通しています。
2. 自分が喪中のときの新年挨拶
2.1 「あけましておめでとう」は控えるのが一般的
自分が喪中の場合、「おめでとう」という祝福の言葉を控えるのがもっとも無難でていねいな対応です。
そのため、以下のような賀詞は使いません。
- あけましておめでとうございます
- 謹賀新年
- 迎春
- 賀正
代わりに、
- 「旧年中はお世話になりました」
- 「本年もどうぞよろしくお願いいたします」
など、気持ちがやわらかく伝わる「非賀詞の挨拶」を選ぶのが安心です。
2.2 自然で温かい「喪中の新年挨拶」文例
どの文例も、書き手の気持ちが負担なく伝わるよう、やわらかい表現に調整しています。
●友人・知人向け
「旧年中はあたたかいお心遣いをいただき、ありがとうございました。
私事ではありますが、昨年身内に不幸があり、
喪中につき新年のご挨拶を控えさせていただきます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。」
●ビジネス(社内・取引先向け)
「旧年中は格別のお力添えを賜り、誠にありがとうございました。
私事で恐縮ですが、喪中につき年頭のご挨拶は控えさせていただきます。
本年も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。」
●LINE/メール向け(短めでやさしい印象)
「昨年は大変お世話になりました。
喪中につき新年のご挨拶は控えさせていただきますが、
本年もどうぞよろしくお願いいたします。」
● 最もシンプルな表現
「喪中につき、新年のご挨拶は控えさせていただきます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。」
● 敬意を保ちたい場面
「私事ではありますが、昨年身内に不幸がありましたため、
年頭のご挨拶を控えさせていただきます。
旧年中のご厚情に心より感謝申し上げます。」

3. 理由を添えると、より誤解のないスマートな挨拶に
「どこまで説明すればいいの…?」と迷う方も多いですが、丁寧にしたい場面では 「簡潔な理由のみ」を添えるのが自然です。
無難で丁寧な書き方
「私事で恐縮ですが、昨年近親者に不幸がございましたため、
喪中につき新年のご挨拶を控えさせていただきます。」
親しくない相手には、よりシンプルに
「昨年身内に不幸があり、年頭のご挨拶を控えさせていただきます。」
誰が亡くなったのか等、詳細を書く必要はありません。
「相手に心配をかけない配慮」としても、このくらいがちょうど良いです。

4. 喪中のお正月はどう過ごす?
喪中の期間は、「お祝いを控える」という気持ちを大切にしながら、いつもより静かに年を越す方が多いです。
ただし、喪中だからといって何もしてはいけないわけではありません。
ご家庭や地域によっても違いますし、「無理をしない過ごし方」 が一番大切です。
ここでは一般的によく質問されるポイントをご紹介します。
4.1 お正月飾りはどうする?
- ◎ 鏡餅・門松・しめ縄などの「お祝いの飾り」 → 控えるのが一般的
- ○ 松の内の装飾を避けて、さりげない飾りだけにするケースも
- △ 地域によっては「気にしない」で飾る家庭も
気持ち的に飾れない場合は、まったく無理をしなくて大丈夫です。
最近は白や落ち着いた色の シンプルなお正月飾り を選ぶ方も増えています。
4.2 初詣は行ってもいい?
結論からいうと、神社・お寺の考え方はさまざまです。
- 神社 → 忌明けまでは控えるのが習わし
- お寺 → 特に制限なし、心を落ち着けに来るのは問題なし
とはいえ、どちらも「絶対に禁止」というわけではありません。
気持ちの整理として参拝する方も多いので、あなた自身の気持ちを優先して大丈夫ですよ。
4.3 新年の挨拶は控えつつも、人とのつながりは大切に
喪中の年はどうしても気持ちが沈みがちですが、周りの方から届くあたたかいメッセージは心の支えになることもあります。
- 「今年もよろしくね」
- 「体調に気をつけてね」
そんな言葉に救われることもありますよね。
だからこそ、あなたから返す挨拶も無理のない範囲で、ていねいに、やわらかくで十分です。

プライバシー保護 | マルウェアなし | 広告なし
5. 相手が喪中のときの新年挨拶
「相手が喪中のとき、こちらはどう挨拶すればいいの?」という質問はとても多いです。
結論からお伝えすると、
「おめでとう」を使わずに、気遣いを込めた挨拶をする ことが一番大切です。
喪中の方は、お祝いの気持ちや明るい言葉を受け取る心の余裕がないこともあります。
だからこそ、こちら側からの言葉選びには少しだけ配慮を添えたいところです。
5.1 避けるべき表現(気づかないと使ってしまいやすいもの)
以下は、喪中の相手には使わないのが無難です。
- 「あけましておめでとうございます」
- 「おめでとう」関連の賀詞(賀正・迎春・謹賀新年など)
- 「今年は良い一年になるといいですね!」など明るすぎる表現
特にビジネスでは、慣れでうっかり使ってしまう人も多いので注意しましょう。
5.2 喪中の相手に使える「あたたかい」 挨拶例
喪中だからといって、まったく挨拶をしないのも不自然です。
ここでは、相手に負担をかけず気持ちのこもった言葉をご紹介します。
ていねいで間違いのない表現
「旧年中は大変お世話になりました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。」
やさしく寄り添う表現
「寒い日が続きますので、どうかご無理のないようにお過ごしください。
本年もよろしくお願いいたします。」
親しい相手に
「ご家族のこと、本当に大変でしたね。
どうかご自身の体調も大切にしながら過ごしてください。
今年もよろしくね。」

6. 喪中であることを知らずに「あけましておめでとう」 と言ってしまった場合
年明けの挨拶は本当に慌ただしく、相手が喪中だと気づかないまま「おめでとうございます」と言ってしまうこともあります。
そんなときも、過度に気にする必要はありません。
ほとんどの方は「言ってしまった本人の気持ち」を理解してくれます。
ただ、ひとことフォローを添えると、より丁寧な印象になります。
6.1 伝えるべきは「気持ち」と「相手を気遣う姿勢」
こんなふうに一言添えると十分です。
「先ほどは失礼いたしました。
喪中のことに気づかず、お祝いの言葉を申し上げてしまい申し訳ありません。
ご家族の皆さまが、心穏やかに過ごせる一年となりますようお祈りしております。」
ていねいに伝えるだけで、ほとんどの誤解は解けます。
6.2 LINEやカジュアルな場面で使える表現
「さっきは気づかずに「おめでとう」って言っちゃってごめんね。
無理のない一年になりますように。」
言い訳をしすぎたり、長文になる必要はありません。
シンプルな一言の方が、気持ちはまっすぐに伝わります。

7. 喪中の相手に贈る「寒中見舞い」 は心を整える機会にも
お正月を過ぎてから喪中だと知った場合、「年賀状を送ってしまった…どうしよう?」と不安になる方も多いです。
そんなときは、寒中見舞いというとても便利で、相手に寄り添える日本らしい習慣があります。
寒中見舞いは、
- 無理なく気持ちを整えたいとき
- 相手の心にそっと寄り添いたいとき
に使える、あたたかさのあるご挨拶です。
寒中見舞いの簡単な文例
「寒さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。
ご家族の皆さまが穏やかに日々を過ごされますよう、お祈り申し上げます。」
※年賀状を送ってしまった場合※
「年始のご挨拶を差し上げましたが、その後喪中と伺いました。
遅ればせながらお悔やみ申し上げます。」
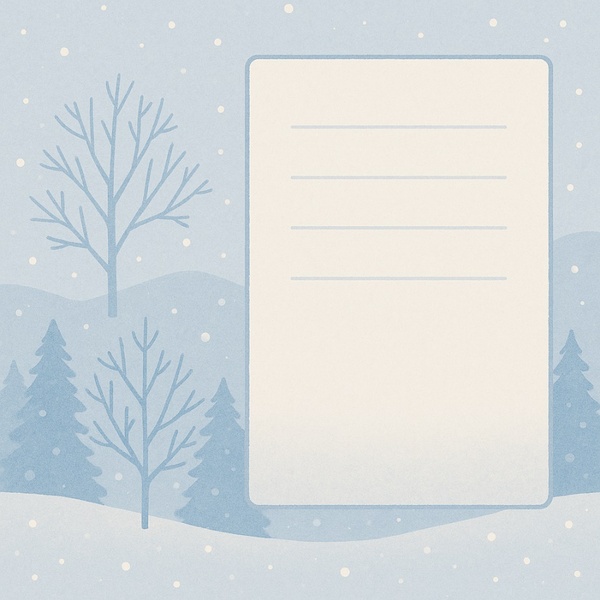
8. 喪中挨拶の文例やテンプレート作成には、PDF管理がとても便利
喪中の時期は、
- メールやLINEでの挨拶文の管理
- 年賀状の代わりに送る寒中見舞いの作成
- ビジネス向けの文例テンプレートの整理
など、実は「文章の準備」がとても多くなります。
そんなときに役立つのが PDFelementです。
私自身、仕事で年末の文例整理をするのですが、
PDFをそのまま編集できるアプリは、やっぱりひとつあると本当に助かります。
【PDFelementでできること】
- PDFの文字編集がそのまま可能
- すでにある文例テンプレートの文字だけ差し替えられる
- 自分用の喪中挨拶集をPDFとして保存できる
- スマホでもPCでも編集できて便利
- 手書き風の署名も入れられる
喪中挨拶や寒中見舞いの文面は、「毎年少しずつ変えたいけれど、基本は使い回したい」という人がとても多いです。
PDFelementを使えば、落ち着いた雰囲気のPDFテンプレートを整えつつ、必要な部分だけ毎年更新できます。
余白にメモを残すこともできるので、「昨年との違い」「誰に送ったかの控え」など、細やかな管理もやりやすくなります。

よくある質問(FAQ)
Q1. 喪中でも初詣に行ってもいいですか?
問題ありません。
ただし、神社では「忌明けまでは控えた方が良い」とされることがあります。
ご本人の気持ちを優先し、無理なく過ごしてください。
Q2.喪中の人に年賀状を送ってしまいました。どうしたら?
焦らなくて大丈夫です。
松の内(1月7日)以降に、寒中見舞いでフォローすれば丁寧な印象になります。
Q3. 喪中の時に「今年もよろしくお願いします」は使っていい?
はい、問題ありません。
お祝いの言葉ではないため、喪中でも安心して使える表現です。
Q4. 忌明け後は「あけましておめでとう」 を言っても大丈夫?
はい、問題ありません。
忌明け(四十九日・百か日など宗派による区切り)が終わってから迎える最初のお正月であれば、一般的な「新年おめでとう」の挨拶を使えます。
ただし、言う側・言われる側の気持ちがまだ整っていない場合もあります。
無理に「おめでとう」を使わなくても構いません。
関連人気記事:【文例あり】喪中の年賀状・新年の挨拶はどうする?基本マナーと代わりの挨拶状を解説
まとめ
喪中の時期は、「新年の挨拶をどうすればいいのか?」と迷ってしまう方がとても多いものです。特に 喪中のお正月挨拶 は、普段以上に言葉選びに気をつけたい場面ですよね。
ですが実際には、
【自分が不幸があった場合新年の挨拶は】
- 「おめでとう」を避ければOK
- 「旧年中はお世話になりました」「本年もよろしくお願いします」で十分
【喪中の人に新年のあいさつをする場合】
- 祝いの賀詞を避ける
- あたたかい言葉で寄り添う気持ちが大切
- 間違えてしまっても、一言フォローを添えれば問題なし
この3つを押さえておけば、ほとんどのケースに対応できます。
そして、毎年使う喪中新年挨拶や寒中見舞いの文例は、PDFでテンプレート化しておくと、心に余裕を持って年末年始を迎えられます。
その際に役立つのがPDFelement。スマホでもPCでも使え、無料試用版もあるので、忙しい時期でもすぐに編集や保存ができてとても便利です。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
あなたの新しい一年が、心穏やかに過ごせるものになりますように。









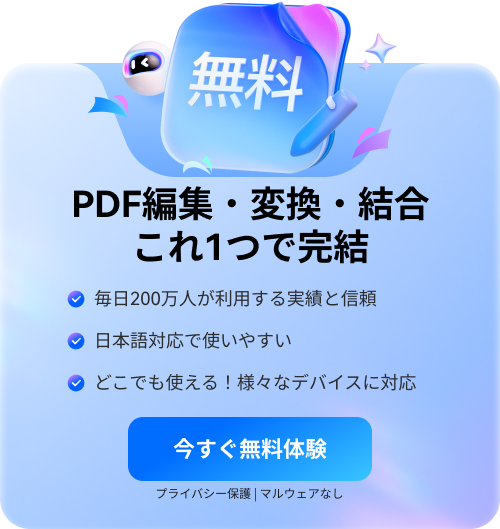
役に立ちましたか?コメントしましょう!